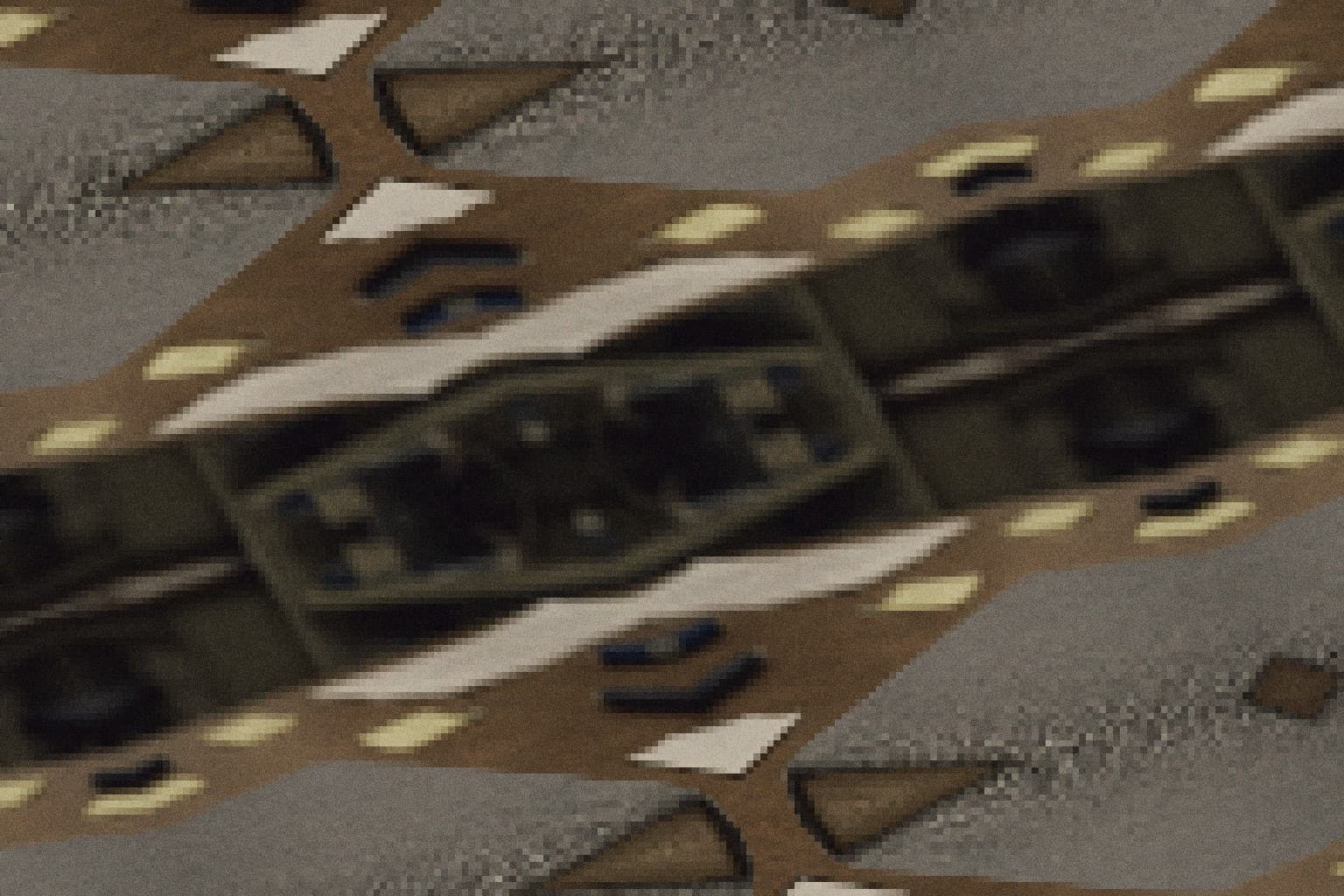「先輩,もうすぐ1時です。装置空きますよ」
リマインダの通知を確認しつつ,私は隣の席の主に告げる。冬が,そして年末の研究会が近付くと,学科共用の分析機器にはひっきりなしに予約が入れられるようになる。装置が汎用的であればあるほど使用権は得づらくなり,他との需要が衝突した場合などは予約フォームに表示される瞬間にアクセスしなければならないほどの事態となる。今回の分析も,そのような争奪戦に勝利して得た権利であった。自分たちはもちろん,敗れていった者たちのためにも1分も無駄にしてはならない,のだが。
紙面を睨みつけるように,先輩は文庫本に没頭していた。グレーのブックカバーが巻かれていてタイトルは分からないが,生返事すら返してこないところを見るに余程集中しているらしい。私だって多少なりとも本は読む。物語に入り込むと周囲のイベントやオブジェクトに対する優先度を無意識のうちに下げてしまう,その感覚に賛同はできるが,時と場所は弁えて欲しいものだ。急かす声が少し荒くなるのも仕方がない。
「もう,いい加減動きますよ。今日見るやつ多いんですから,ちゃっちゃとしましょう」
「え,あ,もうこんな時間。ごめん,はやく準備しないとね」
ぱたぱたと慌てだす先輩に,「ん」と実験用具を詰め込んだ工具箱を突き出す。動きを急に止め,きょとんとした表情のまま「おぉー」なんて言うものだから,何だかおかしくなってしまう。
「優秀優秀。あ,USBメモリは持った?」
「ちゃんとありますよ。…うーん,お願いしてる身分でなんですけど,このバディ制度,やっぱり不便ですよね。前までは私だけで使ってても何も言われなかったのに」
「管理室からのお達しだからねぇ。認定ユーザの許可取るまでは一緒に行かないといけなくなったみたい。ていうか早く試験受けなよ。もう楽勝でしょ?」
うむむと返答を濁らせながら,学生部屋を出る。楽勝と言えるほどではないが,なんとかパス自体はできるだろう程度の自信はある。実際のところ,後期が始まってすぐに受けようと考えてはいたのだ。けれど,先輩に付き添いをお願いするようになってから,ずるずる引き伸ばしてしまっている。オペレートを任せると段違いに綺麗な像を撮ってくれるからだと思う。
「そのうち受けますよ,さすがに。先輩のお楽しみをこうも毎回邪魔するのも不本意ですし」
「そんな心配しなくていいよ。ほら」
道すがら,実験ノートの上に重ねた本を見せつけてくる。どうやら解析のサポートをしてくれるつもりは無いらしく,今回は本当に付き添うだけのようだ。こんな時まで持ってくるのを見るに,今回のはよほど面白かったらしい。また今度貸してもらおうかな,などと考えながら,エレベータのボタンを押した。
* * *
遠いところへ向かおうとしていた意識が,午後4時を告げるチャイムの音で呼び戻される。慌ててマウスに触れ,ラップトップのスクリーンセーバを解除する。目の前に広がるのは作業を始めてからずっと睨んでいたプレゼンテーションソフトの画面。ある一枚のスライド作成が難航したまま,一日が終わろうとしていた。
スライドの主題は決まっているし,示すデータも絞り込んだ。けれど,テキストの内容と配置がどうもしっくりこない。視認性を少し犠牲にして文字の量を多くすれば解決できそうだが,スライド全体で最も重要といえる箇所だからこそ,他に何か手はないかと考えてしまう。日本語は情報圧縮性の高い言語だとどこかで見た気がするけれど,どうせなら研究主題を一言で伝達できるくらいには高密度であって欲しかった。
気分転換にコーヒーでも淹れようと流し台に向かうと,周りから音もなく催促の手が挙がる。普段――あくまで,この研究室の――ならば出研している人間など半分もいない時間帯だが,報告を目前に控えているという現実には逆らえなかったようだ。ひい,ふう,みい,とにょきにょき伸びている腕を数えていると,先輩がまだ来ていないことに気付いた。
湯気の立つマグカップを自分の机に置き,隣の席を見やる。付箋にまみれた上に資料が散乱しているので,天板が隙間からしか見えない。お世辞にも整理されているとは言えないな,などと考えていると,奥の本棚に収められた本と目があった。人の私物に勝手に触れることへのためらいは当然あったが,この部屋に自席をもらってからというもの,事後承諾的な貸し借りは何度もやってきている。ちょっと眺めるだけならば,とブックエンドを少しずらして,引き抜いた。
手にとってまず,その重みと厚さに驚く。私が普段読むものを二,三冊ばかり重ねたら同じぐらいだろうか。表紙はやはり,布地のカバーで見えない。グレーに黒の線が並んだ,あまり飾りっ気のないカバー。以前訊いたところ,この本の為に手作りしたものだと教えてくれた。古本ゆえにもとのカバーがなく,表紙もかなり傷んでいたとか。サイズを測りミシンに向かう先輩を想像して,少しだけ,ほんのすこしだけ素敵だなと思った。気恥ずかしいので思うだけに留めたが。
表紙を捲ろうと,いつも通り左手だけに持つ。小口に添えた親指をわずかにずらすと,挟まれた栞が別のページを開かせた。しまった,と本を閉じるまでに数秒も無かったけれど,そこに記された言葉の,台詞の断片を私の眼は拾ってしまっていた。「4」,「クール」,「拍手」,「待っててください」…。物語を構成する音素が頭の中を巡る。幸い,開かれたページは表紙にかなり近かった。核心的な部分を覗いてしまった可能性は低いだろう。けれど,所定の手続きを経ずに味わってしまうストーリーの気持ち悪さといったらない。買った本に挟まれている小冊子も,目を瞑りながらでないと取れないたちだ。
「おはよう」
ショックで開いた心の隙間に畳み掛けるように声を掛けられ,自分でも分かるくらいに飛び上がる。おそるおそる振り返ると,先輩が立っていた。
「お,おはようござ」
「読んだの?」
「え」
「どうだった?」
私の返事を遮るようにして尋ねてくる。その言葉はどこか平坦で,普段のような熱を帯びてはいない。感想を求められているのではないと,直感で分かった。視線を釘付けにするように瞳がまっすぐこちらに向けられる。横たわった沈黙はどんどん長くなっていく。いつもなら脊髄反射で口をつくのに,今回はやたらと時間がかかった。
「――あ,違う,別に怒ってるわけじゃないよ,ごめんね」
先に口を開いたのは先輩だった。またも私の返事は覆いかぶせられて,とりあえずの謝罪は音にもならずに消えていく。さっきからまともに会話ができていない。ちゃんと息を吸い込んで,今度こそ言う。
「私こそすみません。大事なやつ,勝手に読んだりして」
「謝らなくていいよ。いつも通り,これも読み終わったら貸そうと思ってたんだから。それより」
途中で言葉を打ち切って,私と位置を変わるようにして椅子に座る。私も倣うように自分の席に付き,先輩の方を向く。いつものお喋りの格好だ。
「うん,じゃあ改めて。この本さ,ページ開いて,中の文章…文字でもいいや。読んだりした?」
「読みました。最初の,たぶん20ページくらいのところです」
「どんなシーンだったか覚えてる?」
あれは一瞬の間だったように思うけど,私の無意識は想像以上の情報を得てしまっていたらしい。返答は簡単に出てきた。
「登場人物たちが,何かの会議をしていたと思います」
先輩は,喜と哀が混ざり合ったような表情を浮かべた。
「そっかー。…うん,普通そうだよね」
「ええと,さっきからよく分からないです。ネタバレ踏んでないか確認されてるわけでもなさそうですし」
「うーん,じゃあもう言っちゃうね。」
私から受け取ったその本を両手で持って,科学のいち分野を研究しているこの場所の一角で,先輩はこんなことを言った。
「私,この本に嫌われてるみたい」
* * *
一瞬部屋が凍りついたように思えたけれど,キーボードの打鍵音は絶え間なく響いている。冗談交じりの雑談と思われているのか,そもそも耳を傾けていないのだろうか,クエスチョンマークを浮かべているのは私だけのようだった。きらわれる。嫌われる?
「…本が何をしてくるっていうんですか」
返事の代わりに,先輩は語り始めた。
「前に話したと思うけど,古本屋で見つけたのね,この本。平積みにされてて,ひと目で分かるくらいボロボロだったんだけど,タイトルがなんとなく面白くて手にとってみたんだ。めちゃくちゃ安かったのもあるけどね。家に帰って,ぴったり合うカバーが無かったから,自分で作ってみて。結構良い出来だったから普段よりテンション上がって,読むぞー!ってなってたんだ。」
「それでね」区切るように一呼吸おく。
「とっても面白かったんだと思う。文字通り時間を忘れて読んでた。まあ,よくある感覚だよね。はっとして時計見たら日付変わってて,『あぁ面白かったな,このあとはどうなるんだろうな』とか思いながら布団に入ったとこまで,いつも通り」
「ここからいつも通りじゃなくなるんですか」茶々を入れると,先輩は少し微笑んだ。「いや,この後も同じだよ。君も見てたように,研究室に持ってきて読んだりね。毎日読んで,毎日わくわくして。ずーっといつも通りだった。――この三ヶ月間,毎日,ずっと」
「…え,何かおかしなところが」ありましたか。途中で言葉が口に引っかかった。
「こないだ少し話したじゃない,この本とか,カバーのこと。そろそろ貸してあげようかなーなんて考えてたら,あれ?ってなったんだよね。私はどうしてこの本を読み終えてないんだろうって。帰って,もう一回読んでみて,そこでようやく,気付いたんだ。――自分が読んだ内容を何も覚えてないこと」
* * *
気付いたんだ,と言ったあと,先輩はそれっきり口を閉ざした。
私は相槌を打つタイミングを失って,手の中の本を見下ろす。薄汚れた小口と,丁寧に縫われたブックカバーの端。さっきまで紙の束でしかなかったそれが,急にこちらをちらちらと窺っているように思えてくるから,困ったものだ。
「……全部,ですか」
ようやく絞り出した声が,予想よりもずっと小さかった。
「うん。登場人物の名前も,筋も。何回も読んでるはずなのに,起きると,からっぽ」
先輩は指先でカバーの角をつまみ,表紙をこつこつと叩く。
「でもね,読んでる“あいだ”のことは覚えてるの。面白かったとか,わくわくしたとか,夜更かししちゃったとか。だから,読んでないわけじゃないんだよね」
「疲れてるとかじゃないんですか。寝不足とか」
「まあ,それも多少はあるだろうけどね。最初はそう思ってたよ。で,試しに実験してみたの」
実験,という単語に反射的に背筋が伸びる。先輩は少し笑って続けた。
「普段の読書と同じだと分かりにくいかなって思って,――わざと,二ページだけ読むようにした。寝る前にそこだけ。二ページ進んだらしおり挟んでおしまい。それで,朝起きたら,ノート開いて,何が書いてあったか思い出してみる」
「結果は」
「真っ白」
言いながら,先輩は自分の額のあたりを軽く指でつついた。
「ここのどこかに,なにか通り道みたいなのがある感じがするの。読んでるときは通してもらえるんだけど,寝て起きると,扉が閉まってる。鍵掛けられて,トンネルごと消えてる」
「物騒な比喩ですね」
「研究室の人間だから,ついね」
先輩は自嘲気味に笑ったあと,少しだけ真顔に戻る。
「それで,ノートもつけてみたんだけどさ。書いてるときはちゃんと意味があるんだよ。『会議のシーン』とか『○○が怒られる』とか。でも,次の日読むと,知らない話のメモみたいに見える。ノートの字だけ,私のものなのに」
そこまで聞いて,ようやくさっきの問いの意味が腑に落ちた。どんなシーンだったか覚えてる?という確認。先輩は自分の「忘れる前」の感覚と,私の「読んだばかり」の記憶とを比べようとしていたのだ。
「だから,嫌われてるって言ったのか」
ぽつりと言うと,先輩は肩をすくめる。
「中に招き入れてもらえない感じがするんだよね。ドアの前で立ち話だけして,帰らされるみたいな」
「でも,立ち話はさせてもらえてるんですよね」
「うん,そこは評価してる」
ふたりして小さく笑う。笑ってしまえるくらいには,まだ現実味の薄い話だ。けれど,私の頭の隅では,別の考えがもぞもぞと動き始めていた。
――少なくとも,私は覚えている。
さっき,ほんの数行を盗み見ただけの台詞でさえ,「4」とか「クール」とか,変なキーワードと一緒に脳裏をうろついている。私が読んだときには,きっともっとたくさん残るだろう。もし,本当にこの本が先輩だけを締め出しているのだとしたら。
「じゃあさ」
思考に沈みかけていたところに,自分の声が割り込んだ。驚いて,少し遅れてから,それが自分自身の提案だと気付く。
「一緒に読みませんか」
「今?」
「今はさすがに怒られますけど。例えば,明日とか。ここで,同じところを。最初からでもいいですし」
自分でも何を言っているのか分からなかった。ただ,何かしら形にしておかないと,この話がふわっと空気に溶けて,なかったことになってしまう気がしたのだ。
先輩は少し目を丸くして,それからおどけたように首を傾げた。
「実験協力,ってこと?」
「まあ,そういうことです」
「報酬は?」
「コーヒーくらいなら」
「うん,悪くないね。じゃあ……明日の午後,測定の合間にでも」
そう言って先輩は,ようやくいつもの調子で笑った。
* * *
翌日の午後,四時のチャイムが鳴り終わるころ,研究室の片隅に小さな“読書会”が開かれた。
私と先輩は向かい合って座り,ひとつの本を,それぞれ別の手で支える。変な光景だなと思いつつ,ページをめくる音が,まるで装置のシャッター音みたいに規則的に響いた。
「じゃあ,この章の終わりまでで区切ろうか」
先輩がそう提案し,私は頷く。活字が眼の中に滑り込み,頭の中で意味を持ち始める。会議室,長机,紙コップ,誰かの咳払い。「四クール」と呼ばれる時間単位。「拍手」。待っててください,という台詞。
――やっぱり,おもしろい。
内容そのものの面白さももちろんあるが,それに加えて,隣でページをめくっている人がいるという事実が,妙に胸のあたりをくすぐってくる。先輩は時々,行を追う指先をほんの少し止めて,何かを噛んでいるような顔をした。その表情を盗み見るたび,紙に印刷された文字が,先輩の中でどんなふうに形を取るのかを想像してしまう。
章末まで読み終えると,先輩がぱたんと本を閉じた。
「じゃ,口頭試験を行います」
「いきなり緊張させないでください」
「さっきの部屋,何階にあった?」
「え,部屋番号は出てきてませんでしたよね?」
「うん,そう。つまりちゃんと読んでたね,って話」
くだらない問答で少しだけ和む。そこから数分間,お互いに印象に残った部分を挙げ合った。議題の流れ,誰がどこで言い返したか,出てきた比喩。
先輩は,そのときにはきちんと答えた。むしろ私より細かいところまで覚えているくらいだった。
「じゃ,観察は明日まで持ち越しだね」
先輩はそう言って,本をカバンにしまう。私はノートパソコンを開き直し,測定データとにらめっこを再開した。
翌日。昼過ぎに研究室へ行くと,先輩はいつもの席で資料を広げていた。本は机の端に伏せて置かれている。
「先輩,昨日の実験結果,伺っても?」
「お,ちゃんと覚えてた。ええとね」
先輩はしばらく宙を見上げてから,苦笑まじりに首を振った。
「会議……だったよね。たぶん」
「たぶん,ではなく」
「あと,なんか叩く音がしてた気がする。ひと区切りごとに」
「それ拍手です,たぶん」
「でしょ?なんとなくは残ってるんだけど,誰が誰に何を言ってたかは,きれいに消れてる」
机の上の本は,相変わらず無表情だ。
その後,二,三度同じことを繰り返してみたが,結果は同じだった。読んでいるあいだの先輩はごく普通の読者で,内容も把握している。けれど,一晩経つと,筋だけが砂絵みたいに崩れていく。
「本当に,嫌われてるのかもしれませんね」
冗談めかして言うと,先輩は肩をすくめた。
「ここまで来ると,嫌われてるっていうよりは,意地でも門前払いされてる感じかな。玄関開けたら,毎日同じ廊下しか見せてもらえないみたいな」
「廊下だけ覚えてるんですね」
「うん,壁の色とか,床のきしみ方とか,そこは妙にはっきりしてる」
先輩はそう言って,本のカバーを指先でなぞった。その仕草が,妙に慈しむようで,見ているこちらが気恥ずかしくなる。
――だったら,せめて誰かが,その先に続く部屋のことを覚えておけたら。
頭の中に浮かんだ言葉を,私は自分でも驚くくらいすばやく飲み込んだ。代わりに,無難な提案だけ口に出す。
「……あの,その本,貸してもらえませんか。一晩だけ」
「お?」
先輩の眉が上がる。
「いや,ほら。現象の切り分けというか。先輩以外にも同じことが起きるのか,私には起きないのか,確認した方がいいかなーって」
「なるほど。ちゃんとした実験になってきたね」
先輩はしばらく考えるふりをしたあと,あっさりと頷いた。
「いいよ。そろそろ貸そうと思ってたし。ただし,途中で寝落ちしないこと。夜更かしして体調崩しても,責任取れないからね」
「はいはい」
本を受け取ると,思っていたよりもずっと重かった。厚み以上の重さが,掌に沈んでくる。私はそれを胸に抱え,心持ち早足で研究室を出た。
* * *
その夜,いつもの安アパートの部屋で,私は先輩の本のカバーをそっと外した。下から現れた本体は,思った通り,あちこち擦り切れていて,角は丸くなっていた。手製のカバーの縫い目が,その古さを覆い隠すように,きっちりと全体を包んでいる。
布を傍らに置き,ページをめくる。紙の手触りは少しざらざらしていて,新刊のつるりとした感触とは違っていた。インクの匂いと,ほこりと,どこかで嗅いだことのあるような柔軟剤の匂いが混じっている。
昨日,先輩と一緒に読んだ章を,再びなぞる。会議室,四クール,拍手。何度読んでも,台詞は同じ位置に,同じ濃さで載っている。それを確かめるたびに,胸のどこかが安心する。
ページを進めるうちに,ふと紙の縁が波打っている箇所に気付いた。背表紙に近い部分が,わずかに盛り上がっている。恐る恐る指先を差し込んでみると,数ページ分がばさりとめくれた。
そこは本文ではなく,見返しの余白だった。黄ばんだ紙に,小さな文字が二行だけ書かれている。
万年筆か何かだろうか。少し色の抜けたインクで,こんなふうに記されていた。
――この本は,よく忘れさせてくれる。だから,何度でも最初から,好きな人と読める。
息を吸うのを忘れていたらしく,肺が抗議するように痛んだ。
好きな人と。
私は本を閉じかけ,慌てて止めた。ぱたんと閉じてしまえば,今読んだ行も,この人の「好きな人」も,一緒くたにいなくなってしまいそうだったから。
「……忘れさせてくれる,か」
ぽつりと口に出してみる。先輩が言っていた“嫌われている”という表現とは,少し違う。書き置きの主にとっては,これはむしろ救いだったのだろう。毎回新鮮な気持ちで,同じ物語を,大事な誰かと共有できる。終わらないまま,ずっとそこに居続けられる。
だとしたら。
だとしたら,この本は今も,そうやって誰かをここに留めておこうとしているのかもしれない。ページの向こう側に,先輩を。
自分で書いた文章でもないのに,胸の奥がきゅっと縮んだ。本の中に先輩が閉じ込められてしまうような感覚。もちろん,実際には先輩はそこにいて,明日も研究室で会うのだろうけれど。
私はしばらくそのページを眺めたあと,見返しの裏側に挟むつもりで,メモ帳の紙を一枚ちぎった。ペンを握る手が,少しだけ震えていた。
――ここまでの話は,私が覚えておきます。忘れてしまっても,また一緒に話せますように。
書き終えてから,しばらく見つめる。直接的すぎるかと悩んだが,これ以上言葉を削ると,何が書きたかったのか自分でも分からなくなりそうだったので,そのまま本の中ほどに挟み込んだ。
ページを少しだけめくり,紙の端がほとんど見えないことを確認して,私はようやく本を閉じた。
「おはよう」
翌日,研究室に顔を出すと,同じ挨拶が返ってきた。カバンの中で,昨夜まで読んでいた例の本の角が手の甲に当たる。先輩の席のそばまで歩いていき,なるべく何でもないふりをしてそれを取り出した。
「これ,ありがとうございました」
平静を装って先輩の方へ差し出す。カバー越しに先輩の指が紙片ごと本を受け取っていくのを見ているうちに,胸のあたりが,変にざわざわした。
「どうだった,副作用は」
「特に何も。ちゃんと覚えてますよ」
「いいなあ」
先輩は素直に羨ましそうな顔をする。
「じゃあさ,逆に。私に教えてくれない?」
「教える?」
「昨日の続き。私はもうきっと忘れてるからさ。君の覚えてる話を聞いて,思い出せるかどうか試してみたい」
言いながら,椅子を私の方へ少し回す。視線が期待と不安に半々で揺れている。
――覚えておきます。
昨夜書いた言葉が,胸の裏側から小さく鳴った。私は多少わざとらしく咳払いをしてから,本を開く。
「ええとですね,昨日の会議のあと,橋のシーンがありました。登場人物のひとりが,『四クール待っててください』って言うところ」
「ああ,それ。……そうだそうだ,橋」
先輩の顔にうっすらと光が戻る。曖昧な輪郭だった記憶が,私の言葉を足場にして,ゆっくり形になっていくのが見えるようだった。
その日から,二人の読書は少しだけ形を変えた。
先輩は本を持ってきて読む。翌日には,ほとんど内容を忘れている。私は,同じ本を家で少しずつ読み進めて,覚えている範囲で物語の筋を語る。先輩はその断片から,ところどころ「あ,そこは覚えてる」と拾い上げていく。
以前は先輩ひとりと本との閉じた関係だったものが,ゆるやかに三角形に近づいていく。私は自分の位置を意識しないふりをしながら,語られるたびに少しずつ形を変える物語を,どこか他人事のように聞いていた。
* * *
研究会の準備も,じわじわと佳境に入りつつあった。
難産だったスライドも,何度目かの徹夜の果てに,ようやく形になった。図表の位置,フォントの大きさ,発表時間に合わせた枚数調整――全部が完璧かどうかは自信がなかったが,「もうこれで行くしかない」という諦めにも似た覚悟が,画面の向こうからこちらを見ていた。
「いいじゃん。ちゃんと伝わりそう」
先輩に確認してもらうと,意外にも肯定的な言葉が返ってきた。隣の席には,先輩自身の発表原稿も出しっぱなしになっている。ところどころ赤ペンで書き込まれたメモには,夜遅くまで残っていた形跡がありありと残っていた。
「先輩の方こそ大丈夫なんですか」
「私はまあ,なんとか。質疑で変なところ突かれない限りは」
「変なところっぽいところなら,一緒に何回も練習しましたよね」
「うん。なのにねえ……」
先輩は曖昧に笑って,机の端に置かれた本に視線を落とした。その表紙は,研究会を目前に控えた今ですら,変わらずそこにある。忙しいときほど,読みたくなるのだろうか。
研究会当日。少し遠くのキャンパスまで,皆でぞろぞろとバスに揺られて向かった。
私の発表は中盤のセッションに組まれていた。講義室の照明が落ち,レーザーポインタの光がスクリーンを泳ぐ。自分の声がマイクを通じて少しだけ他人行儀に響き,質問の時間になると,手のひらにじっとりと汗をかいた。
それでも,どうにかこうにか乗り切った。いくつかの質問にはうまく答えられなかったが,致命的な沈黙は生まれずに済んだ。講義室を出たところで,先輩が親指を立てて見せる。
「おつかれ。ちゃんと伝わってたよ」
「ありがとうございます。先輩の番も,もうすぐですよ」
「うん。忘れないようにしないとね」
冗談とも本気ともつかないことを言って,先輩は控室へ向かっていった。
先輩の発表は,全体としてはスムーズだった。いつもと同じ,落ち着いた声で,スライドを順に説明していく。途中で小さな笑いも取って,質疑も淡々とこなす――はずだった。
ひとつだけ,自分でも覚えがある質問が飛んだ。以前,二人で原稿を見直したとき,「ここはきっと聞かれるから,答えを用意しておいた方がいい」と先輩が言っていたポイントだ。
質問が出た瞬間,先輩は一瞬だけ固まった。
ほんの数秒。たぶん客席の多くは気付かなかっただろう。でも,私は手のひらの汗がぶり返すくらい,はっきりとそれを見た。
「……ええと」
先輩は視線をスライドに落とし,数拍置いてから別の切り口で答えを返した。準備していた答えとは違う,その場で組み立てたような言い回し。十分及第点ではあるが,見ているこちらの奥歯がむずがゆくなる。
発表が終わって講義室を出てきた先輩は,少しだけ肩を落としていた。
「おつかれさまです」
「ありがと。……やっぱり見てたよね,さっきのところ」
「まあ」
「昨日まで,何回も練習したんだよ。あの答え。ノートにも書いたし,声にも出して。でも,本番になったら,その部分だけ,するっと抜けててさ」
先輩は,自分の額をこつりと叩く。昨日と同じ場所だ。
「本のせいですかね」
「さすがに,そこまで万能じゃないと信じたいけど」
言って,うっすら笑った。その笑いが,疲労と,どこか諦めに近いものと,それでもどうにか立っていることの証明とでできているのが分かった。
私は何も言えず,ただ自販機で買ってきたペットボトルを差し出した。先輩はそれを受け取り,一口飲んでから,「ま,なんとかなるよ」と小さく呟いた。
* * *
研究会が終わり,年末の慌ただしさが一段落して,冬休みの気配が近づいてきたころ。
「ねえ」
と,先輩が言った。
「バディ制度,そろそろ卒業しなよ」
学科共用の分析装置の予約表には,年明け以降の埋まり具合がぎっしり書き込まれている。先輩の言うとおり,いつまでも付き添いに頼っているわけにはいかなかった。
「試験,受けちゃえば。もう実務はほぼ出来てるんだからさ」
「……そうですね」
本当は,まだ少し先輩と二人で装置室に通いたい気持ちもあった。待ち時間に本を開いてもらって,その横でデータを覗き込む。そんな時間が,思っていた以上に自分にとって大きなものになっていた。
でも,そういう甘さにしがみついていると,いつのまにか本と同じになってしまう気がした。何度も同じところに留まり続けて,先に進めなくなる。
「年明け,一発で受かります」
できるだけ平然とした声で言うと,先輩は「お,かっこいいね」と笑って,私の肩を軽く叩いた。
宣言通り,試験は一回で通った。形式的な筆記と,簡単な口頭試問と,装置の操作実技。どれも,先輩に横で見てもらいながら繰り返してきたことだ。
「おめでとう」
合格通知のメールを見せると,先輩は自分のことみたいに喜んでくれた。同時に,ほんの少しだけさみしそうな顔をしたのを,私は見逃さなかったふりをした。
バディ制度が終わっても,装置室へ完全にひとりで行くことにはならなかった。
「暇なときは,ついていってもいい?」
ある日の予約の前,先輩がそう申し出てきた。
「待ち時間に本読むの,けっこう好きなんだよね。ここだと,変に邪魔も入らないし」
「私も解析楽になるので,ぜひ」
前みたいに機械を操作してもらうことは減ったが,相変わらず,グレーのカバーは私の視界のどこかにあった。先輩はページをめくり,私はパソコンを叩く。ときどき,何かを思い出したように,先輩が本から顔を上げる。
「ねえ,このあとの展開さ」
ある日の待機室で,先輩がぽつりと口を開いた。
「たぶん前にも読んだんだろうけど,どうしても思い出せないんだよね。でも,なんか,知ってる気もする」
「どんなシーンですか」
「ええと……誰かが誰かに,待っててください,って言うところ。拍手があったような気もする。……あれ,これこの前も聞いた?」
「聞きました」
私は笑いをこらえながら,本を受け取った。栞の位置は,私が家で読み終えた少し先に進んでいる。ページの間から,自分のメモの角がわずかに覗いているのが見えた。
「そのシーンのあと,こうなるんですよ」
私は慎重に言葉を選びながら,続きを語る。先輩は真剣な顔で頷いたり,首を傾げたりしながら聞いている。ときどき,目を細めた拍子に,「あ,そこは覚えてるかも」と言う。
そうやって,何度も何度も,同じ話をした。話すたびに,少しずつ違う言い回しになっていく。先輩の反応も,微妙に変わる。そのたびに,本の中身は私の中で別の形に積もっていった。
* * *
やがて,本の最後のページも読まれる日が来た。
ある冬の夕方。外は早くも薄暗く,装置室の窓ガラスには,自分たちの姿と蛍光灯の光だけが映っている。測定の合間に,先輩は静かに本を閉じた。
「たぶん,読み終わった」
「おめでとうございます」
「ありがと。……と言っても,明日の朝には,またほとんど忘れてるのかもしれないけど」
「そのときは,また私が話しますよ」
「そうだね。便利だ」
先輩はそう言って,少しだけ照れくさそうに笑った。
「君は?」
「私ですか」
「読み終わって,どうだった」
突然の問いに,言葉が喉の手前でつっかえる。――どうだった。ずっと,一緒に読んできたはずなのに,感想をまとめることを先延ばしにしていたことに気付く。
「……そうですね」
しばらく考えてから,私はできるだけ無害そうな答えを選ぶ。
「すごく,時間のかかる本でした」
「それはたぶん,私のせい」
「でも,それだけ時間をかけても,読んでて楽しかったです」
先輩は「ふうん」と相槌を打ち,本のカバーを指でつまんだ。
「この本さ」
「はい」
「本当は,嫌ってなんかないのかもね」
「と,言いますと」
「こうやって,私が何度も読みに来るのを,喜んでるだけなのかもしれない。私が忘れてくれないと,何回も最初から読んでもらえないから」
それは,あの夜見返しの文字を読んだときに私が思い至ったのと,ほとんど同じ考えだった。
「ひどい話ですね」
と,私は笑う。
「ずっと,玄関先に立たされ続けるみたいなもんじゃないですか。寒いのに」
「まあ,玄関先も案外,居心地悪くないのかもよ」
先輩は視線を窓の外に向けた。ガラスに映る横顔に,装置のランプの光が点々と重なる。
「それにさ。廊下の向こうの部屋のことは,君が覚えててくれるわけだし」
不意に名前を呼ばれたような気がして,心臓が跳ねた。実際には「君」としか言われていないのに,変な話だ。
「そんな大層なものじゃないですよ。ところどころ,メモってるだけです」
「それで十分。……ああそうだ」
先輩は思い出したように本を開き,ぱらぱらとページをめくる。やがて,見返しに近い箇所で手を止めた。
「これ,君が書いたんでしょ」
指の先に,自分の字があった。――ここまでの話は,私が覚えておきます。忘れてしまっても,また一緒に話せますように。あの夜,震える手で書いた文字たちが,すこし色を含んだ白い紙の上で固まっている。
どう返事をすべきか迷う間もなく,先輩は続けた。
「最初見つけたとき,すごくびっくりした。でも,なんか,すごく安心もした」
「安心,ですか」
「うん。忘れてもいい場所ができた感じ」
そう言って,先輩はページをそっと閉じた。紙と紙の間に挟まれたメモは,もう外からは見えない。だけど,カバーの端から,ごくわずかに,紙の角が顔を出している。
その一辺に,ボールペンの痕が走っているのが分かった。見慣れているはずなのに,自分の字なのか先輩の字なのか,その瞬間だけは判然としなかった。全部は読めない。読めてしまわないように,ぎりぎりのところで線が切れている。
かろうじて拾えたのは,「待」と「て」の二文字だけだった。
「ほら,もう終わるよ」
装置の完了音が,ちょうどいいタイミングで鳴った。
* * *
学生部屋と分析室とをつなぐ廊下は,相変わらず長くて,寒い。床のきしみ方も,壁の色も,何度も歩いて覚えてしまった。窓ガラスの向こうに薄く夕焼けが残っていて,蛍光灯の白がじわじわと勝ち始めている。
背中越しに先輩が言う。
「忘れても,思い出してもらえるって,贅沢だね」
私は何も答えず,ただ歩幅を合わせた。ポケットの中で,USBメモリが小さく鳴る。
さっき閉じた本のことを思い出す。カバーの端から顔を出した紙片の角,あれを書いたひとのことも,書き置きを残した誰かの気持ちも,この本が本当に誰を気に入っているのかも,考え始めるときりがない。
そのどれも,測定ログみたいにきれいに記録しておくことは,きっとできないだろう。明日になればまた,いくつかは抜け落ちて,新しく埋まっていく。
それでも,グレーのカバーがどこかの机の端で開いて,忘れられた物語の続きを,私はまた先輩に話すのだろうと思う。
廊下の先で自動ドアのランプが点る。私は,ほんの少しだけ歩幅を広げて,その光に追いついた。